【二宮尊徳の成功哲学】シリーズ第12回 現地現場主義と二宮尊徳
現地現場主義と二宮尊徳
松沢成文
私は神奈川県知事として、また参議院議員として、政策実現のための手法としてマニフェストを標榜してきた。その中で、勉強すればするほど、経験を積めば積むほど、二宮尊徳の報徳仕法と私のめざすマニフェスト改革にいくつもの類似性があることに驚かされた。私が重視する現地現場主義と同じ発想があるのだ。
(1)「仕法書」と「マニフェスト」
二宮尊徳は、農村改革や武家奉公した服部家や桜町領、相馬藩などの復興再建にあたり、相当過去にまで遡って歳入歳出を調査し、実績に基づいた目標である「分度」を定め、中長期的な目標である「仕法書」を作成し、合理的な計画に基づき実行した。
一方、マニフェスト改革とは、検証可能な数値目票を掲げ、その実現手法や達成期限、財源なども明記して、定期的に達成状況の報告をするというPDCAサイクルを実施するものである。マニフェストは、「政策」中心の政治・行政を創造するツールであり、同時に、選挙や政治、行政を根本から改革する「発火点」でもある。
尊徳は、日本の近代民主政治が100年以上かけてようやく到達したマニフェスト改革を江戸時代後期の社会改革の手法として、すでに実践していたと言っても過言ではない。
(2)「回村など現場調査」と「現地現場主義」
二宮尊徳は、最初に手掛けた大型復興事業である桜町領への赴任にあたって、事前に何度も入念に領地の隅々まで見て歩き、現地の状況を綿密に調査し、問題把握と解決策立案に役立てた。また、着任後も自ら早朝より「回村」し、現場の状況把握に努めるなど、直接の現場把握・現場尊重は、終生変わらぬ手法であった。
私も、現地調査や地域住民との対話から政策や改革を立案するという「現地現場主義」を徹底して実施してきた。マニフェストは重要だが、それのみに依拠して政策を進めるだけでは、十分でないことは当然であろう。政治の課題は日々生起し、新たな変化に対応していかねば、地域住民の生活を守り、向上させることはできない。そこで、知事時代の私は、「ウィークリー知事現場訪問」と称し、直接現場に出向き現地を調査して、その場で地域住民や当事者、現場職員と対話を交わしながら、政策を立案し、政治を推進するという方法をとった。現代版の「回村」というべき現場訪問は、私にとっても政治活動の原点である。
(3)「芋こじ」と「タウンミーティング」
二宮尊億は、庶民の知性、感性、判断力というものを、高級武士のそれにも劣らぬものとして評価し、信用した。村ごとに毎月、日を決めて自主的な寄合いを持つようにし、村役人や地主には発言を控えさせ、できるだけ農民から意見を出させるようにした。こうした会合を「芋こじ」と呼び、出された意見を積極的に取り入れたという。
私も現地現場主義の実践の一つの手法として、重要政策について、直接皆さんの意見を伺う場として、各地で「ふれあいミーティング」と呼ぶタウンミーティングを実施してきた。また、「ウィークリー知事現場訪問」で現場を訪問した際も、必ず現場の人々と意見交換を実施するように心がけた。これらは、常時、県民各層の意見を伺い、県民本位の県政を進めるうえでの重要な手法であった。また、国政に復帰してからもタウンミーティングを開催し、全国各地を訪れ、対話を重ねてきた。
このように、私は尊徳の生き方や考え方に共鳴するのはもとより、清廉で民主的、かつ現場重視の合理的な改革手法や輝かしい功績には驚嘆することばかりだ。神奈川県知事として、参議院議員として、政治家として師表と仰ぐべき偉大な存在であった。
【出展:拙著「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)】


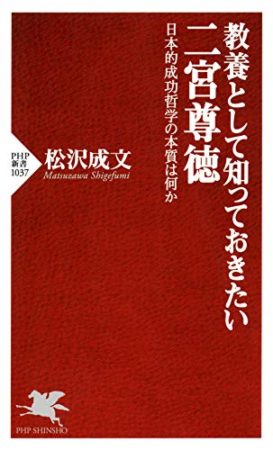





 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る