【二宮尊徳の成功哲学】シリーズ第9回 ピーター・ドラッカーも尊徳を礼賛
ピーター・ドラッカーも尊徳を礼賛
松沢成文
岩崎夏海の小説「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」は、ドラッカーの名著「マネジメント」の内容を部の改革に生かす内容で話題を集めた。改めてドラッカーブームに一役買ったようだ。
現代経営学の発明者といわれるピーター・ドラッカーも、日本的経営の素晴らしさと、その始祖ともいうべき二宮尊徳を信奉していたといわれる。
ドラッカーは1909年、オーストリア・ウィーン生まれ。ロンドンでのエコノミストを経て、渡米。以降、ビジネス界で最も影響力を持つ思想家として知られる。すこし年配の方なら、1970年代に日本でベストセラーになった「断絶の時代」や「見えざる革命」などの著書を思い出されるのではないだろうか。
さて、時代も国も異なる二宮尊徳とドラッカーだが、この二人には、経営コンサルタント的な面で、あるいはマネジメントの先駆者として、多くの似通ったところがあるのに驚かされる。
尊徳が生きた時代は、江戸後期の政情不安な時期で幕藩体制にほころびが生じ、また、商品経済が浸透する中で人々の生活が困窮していた。加えて、冷害や洪水などの災害により各地で飢饉が発生し、特に北関東や東北の農村は疲弊していた。尊徳は、生家を再興したノウハウを生かして、綿密な現地調査により生産能力が阻害されている原因を探り出し、目標値を立て、技術力をも駆使し、戦略的に遂行することで、潜在していた生産能力を呼び覚まし、600余村や武家、藩の再生に成功する。
一方、ドラッカーは、マネジメントのコンセプトとして、①生産性向上のための科学的管理法②組織構造としての分権組織③人を組織に適合するための人事管理④明日のためのマネジメント開発⑤管理会計⑥マーケティング⑦長期プランニングの7つを挙げている。企業にとって、マーケティングとイノベーションの必要性を説いている。まさに、報徳仕法の計画性、効率性、合理性と共通するコンセプトである。
さらに、「企業=営利組織でない。利益と社会貢献は矛盾するとの通念があるが、企業は、高い利益を上げて、初めて社会貢献を果たすことができる」と述べているが、これは尊徳の「道徳経済合一説」や渋沢栄一の「論語と算盤」の趣旨に相通じるものを読み取れる。
事実、ドラッガーは晩年、尊徳の報徳仕法を研究するために大学の最高顧問になる予定だった。「先進国や社会主義国にも適応できる思想だ」と高く評価し、英語文献を根こそぎ送ってほしいと要望していたそうだ。
なお、ドラッカーは「マネジメント(エッセンシャル版)」(2001年)の発行に当たり、日本の読者に次のような傾聴すべきメッセージを残している。
「私は、21世紀の日本が、私の本書に多くのものを教えてくれた40年前、50年前の、あの革新的で創造的な勇気あるリーダーたちに匹敵するような人たちを再び輩出していくことを祈ってやまない――。」
それら日本の偉大なビジネスリーダーのみならず、経営学の元祖ドラッガーも二宮尊徳を信奉していたのである。
先般、偶々、JR東日本発行の広報誌「トランヴェール」(2022年2月号)を手にしたところ、何と18ページにわたって「渋沢栄一も学んだ二宮金次郎」と題する特集があったのに驚かされた。その中で、磯田道史国際日本文化センター教授(専攻は日本社会経済史)は、「(尊徳が活躍した)その時代と、2000年代後半以降の現代日本の状況がよく似ている」と説かれている。
ビジネスパーソンの多くは、二宮尊徳の業績に、長く低迷する日本経済の活路を見出そうとしているようだ。
【出展:拙著『教養として知っておきたい二宮尊徳』(PHP新書)】


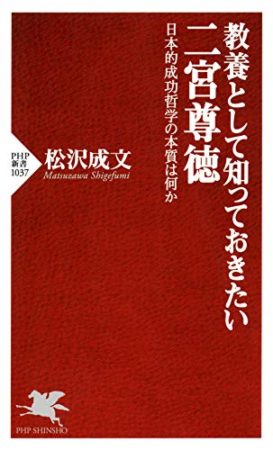





 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る