No.24【二宮尊徳の経営哲学】「富に至る橋」に学ぶ、渋沢栄一が継承した報徳の精神
二宮尊徳の思想は、農村復興の枠を超え、近代日本の資本主義を牽引した多くの財界人に多大な影響を与えました。中でも、「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一は、尊徳の「道徳経済一元論」を自らの経営哲学「論語と算盤」として昇華させ、その精神を後世に伝えた最大の功労者の一人です。
尊徳は以下のように、貧しい者がただ富める者を羨む愚かさを、橋のない川を渡ろうとする行為にたとえて説きます。
「貧者が天分の実力をわきまえず、みだりに富者をうらやみ、そのまねをしようとする。(中略)人がもし富者のまねをしたいと思うならば、まず富を得るための橋をかけることが必要である。富を得るための橋とは何のことか。分度を守ることと節倹がそれである」(『二宮先生語録』斎藤高行著より)
これは、成功を夢見るすべてのビジネスパーソンへの普遍的なアドバイスです。成功者の華やかな姿だけを真似るのではなく、まず、その成功を支える地道な努力、すなわち「分度(規律ある予算管理)」と「節倹(コスト意識)」という「橋」を、自らの手で架けなければならないのです。
この尊徳の教えに深く共鳴したのが、渋沢栄一でした。渋沢は、尊徳思想の四つのキーワード「至誠」「勤労」「分度」「推譲」を自らの行動規範としました。特に、渋沢の「商業における公益と私益は一つである」という考えは、尊徳の「道徳経済一元論」と完全に一致します。企業は私益を追求するだけでなく、その活動を通じて公益に貢献するべきであるという、極めて高度なCSRの精神です。
渋沢は、その生涯で日本銀行の創立や500社近い企業の設立に関与し、日本の近代化に絶大な貢献を果たしました。それは、尊徳が600余りの農村を復興させたのと同様の、まさに「報徳仕法」の実践でした。さらに、早稲田大学や一橋大学などの設立に資金面で協力したことは、「(中略)できるかぎり社会のために協力しなければならぬと思う」という尊徳の推譲の精神そのものです。
渋沢栄一は、尊徳の「道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は戯言である」という哲学を、「論語と算盤」という言葉で現代に蘇らせました。尊徳から渋沢へと受け継がれたこの思想は、企業とは、単に利益を上げるための組織ではなく、高い倫理観を持ち、社会全体の発展に貢献する公器であるべきだという、時代を超えた普遍的な経営の理想像を、私たちに示しています。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。
お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。
#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川
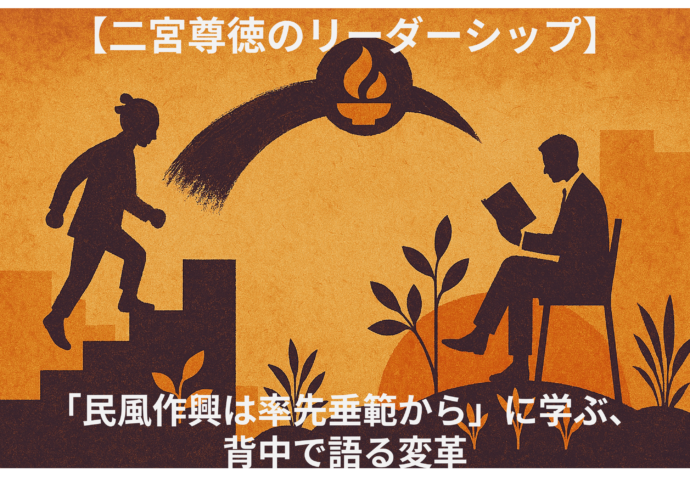





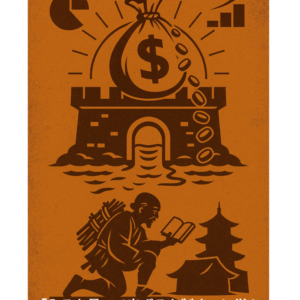

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
