No.23【二宮尊徳の職業倫理】「家業は出精、欲は抑制」に学ぶ、日本的経営の源流
二宮尊徳の思想は、単なる農村復興の技術論にとどまらず、日本における近代的な職業倫理、ひいては資本主義の精神そのものの礎を築きました。その核心は、「家業」と「欲」を明確に区別し、勤労の尊さを説いた点にあります。これは、マックス・ウェーバーが分析したプロテスタンティズムの倫理観とも通底する、極めて近代的な思想でした。
尊徳は以下のように、多くの人が混同しがちな「家業」と「欲」の違いを明確に定義します。
「世間には家業と欲とを混同して、区別を知らぬ者がある。(中略)家業は出精せねばならぬものだ。怠っては済まぬものだ。欲は、これと違って、押さえねばならぬものだ」(『二宮翁夜話』福住正兄著より)
これは、現代経営における「事業目的」と「経営者の私利私欲」を分ける考え方そのものです。「家業への出精」とは、自らの職業倫理に基づき、顧客や社会のために全力を尽くす尊い行為です。一方で、「欲」とは、その職業倫理を踏み越えた個人的な強欲を指します。尊徳は、あらゆる職業人に対し、自らの職務に誠実に励むことを奨励する一方で、その職務を利用して私腹を肥やすことを厳しく戒めたのです。
では、なぜ「家業への出精」が重要なのでしょうか。尊徳は、その結果として、富は自然とついてくると説きます。「農家は、作物のために一途に努めて、朝夕力を尽くし心を尽くしていれば、自然と、願い求めずに穀物が蔵に満ちる」。これは、「良い仕事をすれば、利益は後からついてくる」というビジネスの王道を示しています。顧客のために誠実に製品やサービスを作り込めば、自然と市場からの評価を得て、新たなビジネスチャンスが舞い込んでくるのです。
尊徳のこの「道徳と経済の融合」という思想は、明治以降の日本の資本主義の発展に計り知れない影響を与えました。渋沢栄一が国家財政の参考にし、安田善次郎が自らの経営哲学に取り入れたのを皮切りに、豊田佐吉、御木本幸吉、そして松下幸之助、土光敏夫といった、日本を代表する多くの名経営者たちが、尊徳の教えを自らの経営理念の根幹に据えました。彼らは、単に利益を追求するのではなく、勤労を通じて社会に貢献するという高い職業倫理を貫いたのです。
尊徳の「家業は出精、欲は抑制」という教えは、利益追求(経済)と社会貢献(道徳)は二律背反ではなく、融合させることができるという、「道徳経済一元論」の思想の根幹です。これこそが、日本的経営の強さの源流であり、現代のCSRやサステナビリティ経営にも通じる、時代を超えた普遍的なビジネス哲学なのです。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。
お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。
#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川






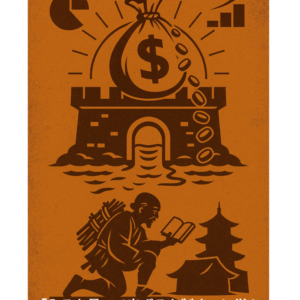

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
