No.19【二宮尊徳の人事論】「正直者を引き立てる」に学ぶ、組織を再生させる人材登用の神髄
あらゆる組織改革の成否は、最終的に「人」で決まります。江戸時代の改革者、二宮尊徳は、その思想と実践の中で、組織を再生・活性化させるための、極めて実践的かつユニークな人事哲学を確立しました。その核心は、目立たずとも誠実に組織を支える「正直者」を発掘し、彼らが報われる「仕組み」を構築することにありました。
尊徳は、組織再生の要諦は、埋もれた人材を発掘することにあると説きます。彼は組織における人材を土地の開拓にたとえ、以下のように語りました。
「村里の復興には正直者を引き立てることが肝心で、土地の開拓には肥えた土を盛り立てることが肝心だ」(『二宮翁夜話』福住正兄著より)
肥沃な土が豊作に不可欠であるように、組織の土台を支えるのは、目立たなくとも誠実に日々の業務に取り組む「正直者」たちです。しかし、彼らはしばしば自己アピールが上手い社員の陰に隠れがちです。リーダーの最も重要な役割の一つは、この埋もれた「宝」を意図的に探し出し、表舞台に引き上げることにあると考えたのです。
そのための具体的な手法が、当時としては画期的な「表彰制度」でした。評価は上司が一方的に行うのではなく、同僚同士の「投票」という、現代の「360度評価」にも通じる民主的なプロセスを採用しました。さらに、その副賞は名誉だけでなく、受賞者の事業拡大に直結する「無利息金の旋回貸付け」という、極めて実利的なインセンティブでした。この仕組みは、「真面目に働けば、仲間から認められ、かつ経済的にも報われる」という公正な文化を組織内に醸成し、人々の労働意欲を劇的に向上させました。
尊徳はまた、人材を「なまくら刀(善人)」と「よく切れる刀(悪人)」にたとえ、リーダーによる使い分けの重要性を説いています。能力は高いが倫理観に欠ける「よく切れる刀」は、短期的には成果を上げるかもしれませんが、長期的には組織を蝕むリスクがあります。彼は、持続可能な組織を築くためには、誠実で信頼できる「なまくら刀」、すなわち「善人」を中核に据えなければならないと結論づけています。
結局、尊徳の人事論が示すのは、リーダーの役割が単なる才能の発掘ではなく、公正で透明性の高い評価制度を設計し、誠実な貢献が正当に報われる文化を育むことにある、という真理です。これこそが、組織全体のエンゲージメントを高め、持続的な成長を実現する唯一の道なのです。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。
お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。
#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川
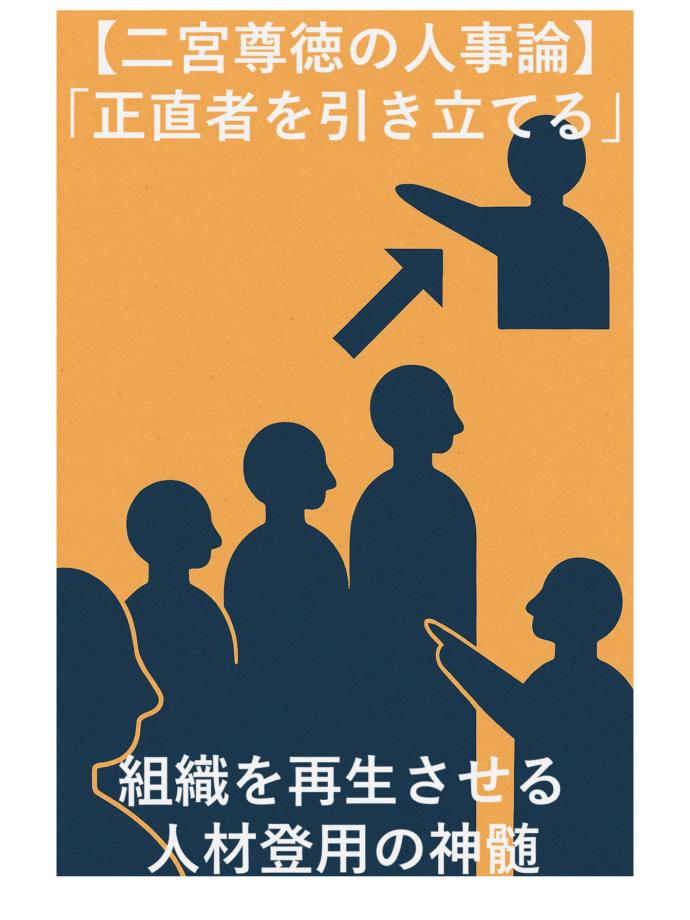





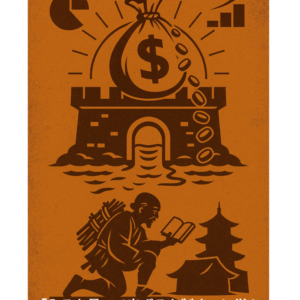

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
