No.16【二宮尊徳のレガシー論】「わが説を千年の後にも伝えてもよい」に学ぶ、実践者の言葉
二宮尊徳の思想の根底には、常に「実践」がありました。彼が自らの言葉に不変の価値があると確信していたのは、その言葉が揺るぎない「実践」という事実によって裏打ちされていたからです。これは、リーダーが遺すべき真のレガシー(遺産)とは何かを、私たちに力強く問いかけます。
尊徳は、行動を伴わない知識を「空言」として以下のように痛烈に批判しました。
「経書を読んで身を修めず、いたずらに口腹を養う足しにする者は、縄をなって口腹を養う者と何の相違もない」(『二宮先生語録』斎藤高行著より)
これは、どんなに優れた理論や戦略を語っても、自ら行動し結果を出さなければ何の価値も生まないという、現代ビジネスにおける「言うだけ番長」への厳しい警鐘です。彼は、世に溢れる書物の多くが「実際の役に立たぬは当たり前だ」と述べ、現場での実践経験に裏打ちされていない理論の空虚さを見抜いていました。
一方で、尊徳は自らの教えには「千年の後に伝えても、断じて恥ずかしいことはない」と、絶対的な自信を持っていました。
「私の場合はそうではない。荒地を開墾し、廃家を復興してから後にこれを書き、衰村を取り直し、廃国を復興してから後にこれを記すのであるから、名実ともに備わっている」(『二宮先生語録』斎藤高行著より)
彼の言葉に力があるのは、自らが過酷な現場で汗を流し、具体的な成果を出したという揺るぎない「事実」に基づいているからです。これは、現代のリーダーが発するメッセージの重みにも通じます。現場を知らず、自ら手を汚したことのないリーダーの言葉は誰の心にも響きませんが、困難なプロジェクトを成功に導いた経験を持つリーダーの言葉は、組織を動かす力を持つのです。
尊徳の偉大さは、その思想を単なる言葉で終わらせず、未来に伝える「仕組み」を構築した点にもあります。彼は晩年、斎藤高行ら高弟に下記著書の編纂を託しました。
・『二宮先生語録』斎藤高行著
・『二宮翁夜話』福住正兄著
・『報徳記』富田高慶著
その思想と実践は、今日、小田原市の「報徳博物館」や「尊徳記念館」といった施設によって、多くの人々に学びの機会を提供し続けています。
尊徳の生涯は、真に価値ある言葉とは、常に「実践」の中から生まれるものであるという不変の真理を私たちに教えてくれます。リーダーとは、雄弁に語る人である前に、まず黙々と「行う人」でなければならないのです。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。
お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。
#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川
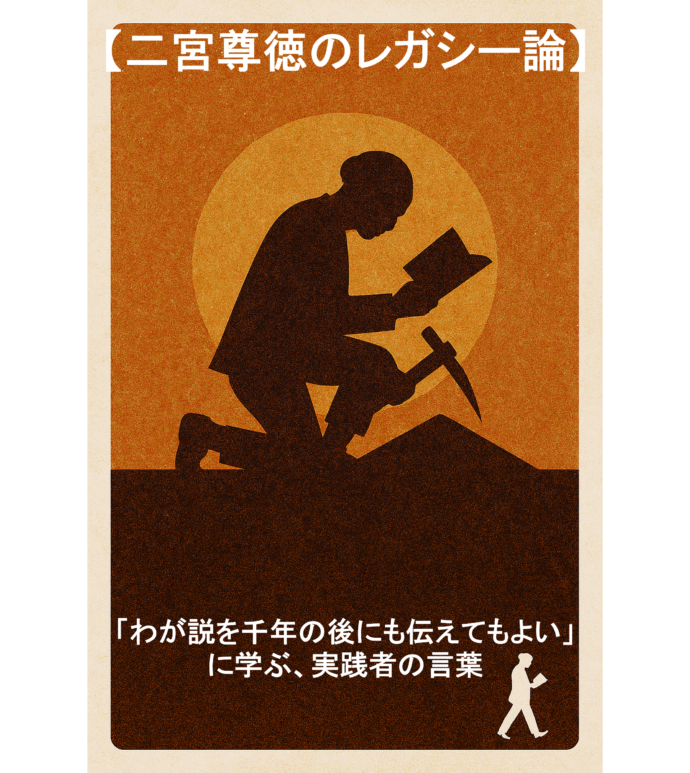


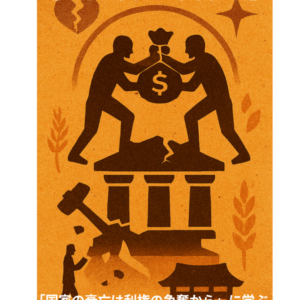

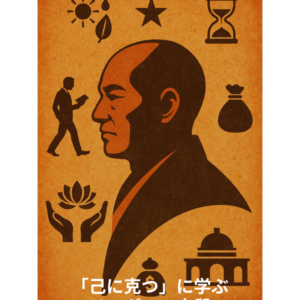
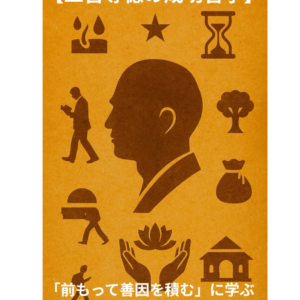

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
