No.12【二宮尊徳の永続経営】「分度による推譲は永安の道」に学ぶ、企業のレガシー
二宮尊徳の哲学の最終目的地、それは「永安の道」、すなわち個人と組織が永遠に安らかに存続するための道です。その鍵は、「分度」によって生み出された余剰を、未来と社会のために戦略的に「推譲」することにありました。
尊徳は、成功した組織が陥りがちな「成長の罠」と、その脱出法を老木にたとえて説きます。
「樹木も老木となると(中略)萎縮して衰えるものだ。このとき大いに枝葉を切りすかせば、来春は枝葉がみずみずしく、美しく出るものだ。人々の身代もこれと同じだ。(中略)不足を生じて分限を引き去ることを知らなければ、ついに滅亡する。(中略)推譲の道とは、百石の身代の者が五十石で暮らしを立てて、五十石を譲ることである。(中略)家産を永遠に維持すべき道はこのほかにない」
(『二宮翁夜話』福住正兄著より)
これは、現代経営における「事業ポートフォリオの見直し」と「選択と集中」の重要性を示しています。事業が拡大すると、組織は非効率な部門(老木の枝葉)を抱え込み、やがて衰退します。尊徳の処方箋は、戦略的なリストラクチャリングを行い、「収入の半分で経営し、半分を未来に譲る(推譲する)」という規律を守ること。これこそが、企業を永続させる唯一の道だと説くのです。
さらに尊徳は、「推譲」が単なる美徳ではなく、成功した者(富貴の者)に課せられた社会的責務であると強調します。成功した企業には、その富を社会に還元(推譲)し、社会全体の持続可能性に貢献する責任があるのです。そして、その責任を果たすことこそが、結果的に自社の永続的な繁栄に繋がるという、壮大な好循環を示唆しています。
尊徳自身、その生涯をこの哲学の実践に捧げ、600もの農村を復興させながらも、私有財産を一切残さず、その全てを未来に残しました。
近代の政治家・後藤新平は「金を残すのは下、事業を残すのは中、人を残すのは上」という言葉を残しました。尊徳は、農村復興という偉大な「事業」を成し遂げ、そして何よりも「報徳」という思想と、それを実践する多くの「人」を後世に残したのです。
尊徳の生き様は、経営者の究極の目的が自らの富を築くことではなく、社会に貢献する事業を成し、未来を担う人と文化を育てることにあるという、リーダーが目指すべき最も高潔な「レガシー(遺産)」のあり方を示しています。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。
#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川






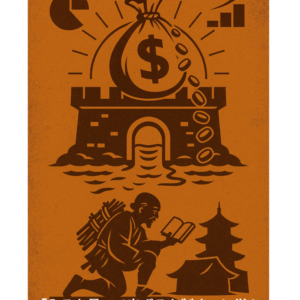

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
