No.27【二宮尊徳のキャリア論】「ためにせずに勤める」に学ぶ、登用の原理
キャリアにおける成功や昇進は、どのようにして得られるのでしょうか。二宮尊徳の生涯は、出世や名声を目的とせず、ただひたすら目の前の職務に全力を尽くす「ためにせずに勤める」という姿勢こそが、結果的に人を高みへと押し上げるという、キャリア形成の普遍的な真理を示しています。
尊徳は以下のように、古代中国の聖人を例に、地位を求める心そのものが、人を道から外れさせると説きました。
「シナ古代の帝王の舜や禹は、帝王になりたいと願ってなったのではない。ただ一途に勤めるべきことを勤めただけの話である」
「村長になろうと思って村長になったりしては、その家も村も決して治まらない。なぜかと言うと、こうしたいという欲望からするときは、謀略とか手管を用いるからだ」(『二宮翁夜話』福住正兄著より)
これは、現代のキャリア論における「内発的動機づけ」の重要性を示しています。昇進や報酬といった外発的な動機を第一にすると、人は近視眼的になり、社内政治や駆け引きに走り、結果として周囲の信頼を失います。一方で、仕事そのものへの貢献や自己成長という内発的な動機に基づいて行動する人は、自然と周囲からの評価を得て、結果的に高い地位へと押し上げられるのです。
では、どうすれば他者から評価され、登用されるのでしょうか。尊徳は以下のように、その答えは自分自身の中にあると説きました。
「官職につけないと、すぐに、明君がいないからとかいうが、間違いも甚だしい。(中略)山の芋が藪にあれば、人は探し出して採る」(『二宮先生語録』斎藤高行著より)
これは、現代のキャリア戦略における「自身の市場価値を高める」という考え方そのものです。組織や上司を嘆く前に、まずは自分自身が、他者にとって圧倒的な価値を提供できる存在になるべきです。確固たる価値さえ身につければ、求めずとも自ずと機会は巡ってくるのです。
尊徳自身の人生は、まさにこの哲学の実践でした。小田原藩への登用時には身分制度の壁に阻まれ、幕府に登用された際も単なる「土木技術者」として扱われるなど、その能力に見合った評価を常に得られたわけではありませんでした。しかし、彼はそうした不遇を意に介さず、与えられた使命に「ためにせずに勤め」ました。
彼の生き様は、周囲の評価や役職に一喜一憂することなく、ただひたすら目の前の職務で誠実に価値を創造し続けることこそが、いかなる逆境をも乗り越え、最終的に揺るぎない評価を勝ち取るための、唯一にして最も確かな道であることを、私たちに教えてくれます。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。
お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。

#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川





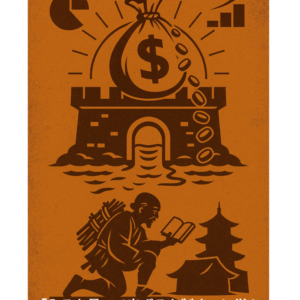

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
