No.18【二宮尊徳のリーダーシップ論】「不動心」が人を動かす
あらゆる組織改革には、抵抗や困難がつきものです。短期的な成果を求められ、内外からの批判に晒される中で、リーダーはどのようにして組織を導けばよいのでしょうか。その答えのヒントが、二宮尊徳が桜町領(現・栃木県真岡市内)の復興という絶望的な事業を成し遂げた際の「不動心」にあります。
覚悟としての「不動心」
桜町領(現・栃木県真岡市内)の復興は、荒れ果てた土地と離散した人心という最悪の状況から始まりました。尊徳は、この事業に着手する際の覚悟をこう語っています。
「『成功してもしなくても生涯ここを動くまい』と決心したのだ。たとえ事故で背中に火が燃えつくような場合に立ち至っても、決して動くまいと、死をもって誓ったのだ。(中略)私が今日までやってこられたのは、不動心の堅固という一つにある」(『二宮翁夜話』福住正兄著より)
これは、現代のリーダーに求められる「パーパス(存在意義)への揺るぎないコミットメント」そのものです。 どんな困難に直面しても、決して逃げ出さないというリーダーの「不動心」が、周囲に安心感を与え、人を動かす原動力となるのです。
本質を見抜く「不動心」
改革の秘訣を問われた尊徳は、名代官として知られた江川太郎左衛門(第36代、反射炉でも有名)にこう答えています。
「あなたは代官としての御威光があるから何事でも大変しやすいでしょう。私はもとより無能無術です。けれども、(中略)〝茄子をならせ、大根を太らせる〟仕事を確かに心得ていますので、この道理を手本として、怠らずに努めているにすぎません」(『二宮翁夜話』福住正兄著より)
これは、小手先の経営テクニックや流行りの理論(術)に頼るのではなく、事業の本質的な価値(道理)を追求することの重要性を示しています。 顧客に価値を提供し、良い製品やサービスを作るという「茄子をならせ、大根を太らせる」地道な実践。その本質を見失わない「不動心」こそが、持続的な成果を生み出すのです。
すべてを包摂する「不動心」
しかし、尊徳の改革は、反対勢力の妨害などにより一度は頓挫しかけます。失意の彼は成田山(新勝寺)にこもり、そこで「一円観」という新たな境地に至ります。これは、善悪二元論を超え、対立するものですら一つの円の中にある相対的な存在と捉える、包括的な世界観です。
この悟りによって、尊徳の「不動心」は、単なる頑固さから、対立者すらも包み込み、動かしていく真の強さへと昇華しました。 彼の揺るぎない姿勢は、やがて抵抗勢力の心をも動かし、改革は再び軌道に乗ります。
現代のリーダーシップにおいても、この三つの「不動心」は不可欠です。
①事業のパーパスに対する揺るぎない「覚悟」
②小手先の術に惑わされず、事業の「本質」を追求する力
③組織内外の対立すらも包摂し、大きな目的に向かわせる「器」
これらを備えたリーダーの「不動心」こそが、困難な時代を乗り越え、人を、そして組織を動かす最大の力となるのです。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。
お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。
#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川
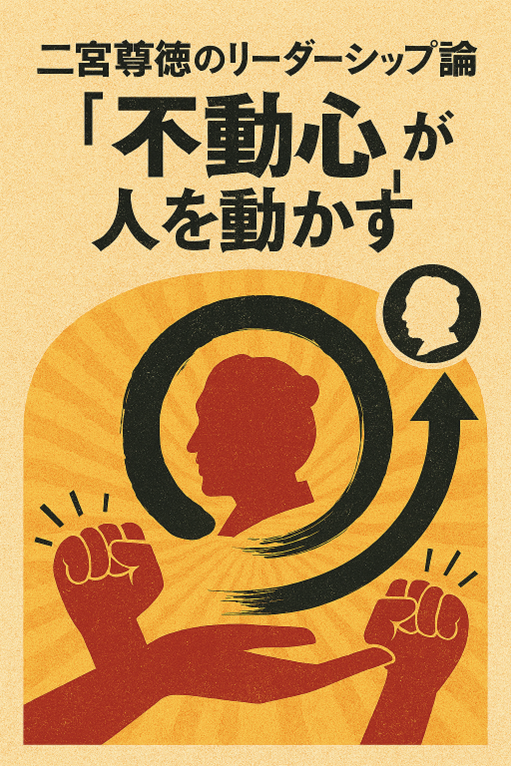





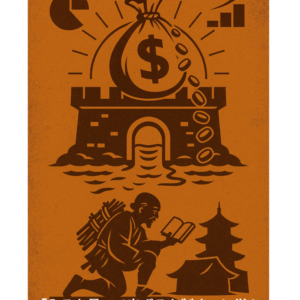

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
