No.15【二宮尊徳の経営哲学】「富貴は天にあり」に学ぶ、道徳と経済の融合
二宮尊徳の思想の究極、それが「道徳経済一元論」です。これは、「道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は戯言である」という信念のもと、倫理と利益を分断せず、一つのものとして追求する、持続可能な経営の最高理念です。
尊徳は富貴(成功)の本質について、以下のように名声や利益を直接追い求めることの危険性を指摘しています。
「世に用いられたい、立身出世をしたいと願うときは、道の本質にたがい、道の本体を失うようになる」
「ただただ、よくこの道を学び、体得して、自らよく勤めさえすれば、富貴は天から来るのだ。決して他に求めるでない」(『二宮翁夜話』福住正兄著より)
これは、自社の利益を第一目的にするのではなく、まず社会における存在意義(道)を追求すれば、利益や評価(富貴)は後からついてくるという、現代の「パーパス経営」そのものです。彼はきこりと炭焼きを例に、「その職業さえ勉励すれば、白米も自然に山に登るし、海の魚も、里の野菜も、酒も油も、みんなひとりで山へ登るのだ」と語り、報酬を目的とせず、ただ自らの職務に勉励することの重要性を説いています。
この思想は、福住正兄が総括するように、「道徳をもって体となし、経済をもって用となし、この二つを至誠の一つをもって貫く」という「道徳経済一元論」に結実します。尊徳は、経済活動(利)を道徳(義)の下に置く従来の儒教の考え方を、生産者ではない武士の論理として「戯言」と断じ、経済活動こそが道徳を実践するための不可欠な土台であると考えました。
その核心が「経済を伴わない道徳は戯言であり、道徳を伴わない経済は罪悪である」という言葉です。これは、利益を度外視した社会貢献活動は持続可能ではなく、逆に、倫理観を欠いた利益追求は社会悪であるという、現代企業のCSRやSDGsへの取り組みの本質を鋭く突いています。
奇しくもこの思想は、『国富論』のアダム・スミスの「富とは貨幣の量ではなく、生活資料の量である」という考えと類似しており、企業が生み出すべきは社会を豊かにする「価値」そのものであることを示しています。尊徳の教えは、ビジネスとは、社会を豊かにするという「道徳」と、その活動を支える「経済」を、「至誠」の心で統合する営みであるべきだという、時代を超えた普遍的な経営の理想像を私たちに示しています。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。
お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。
#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川
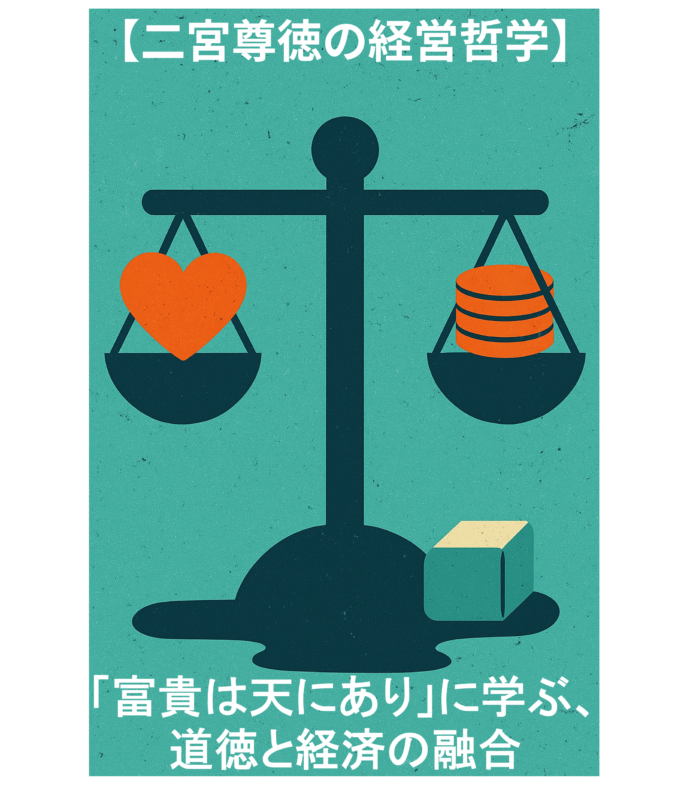





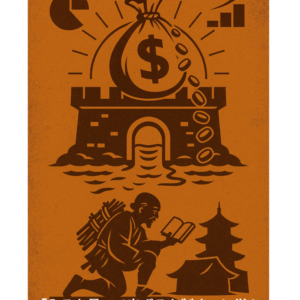

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
