No.8【二宮尊徳の因果論】「蒔いたものが生える」に学ぶ、長期的経営の原理原則
二宮尊徳の思想の根底には、「蒔いたものが生える」という、シンプルで強力な「因果の理法」があります。これは単なる道徳論ではなく、あらゆるビジネスの成否を左右する普遍的な経営哲学です。
尊徳は以下のように、人々の願いが叶わない理由を、種蒔きにたとえて説きます。
「世人の欲求することは、その実行することと反対である。(中略)ひえを蒔けばひえが生え、米を蒔けば米が生える。(中略)今もし、ひえを蒔いて米を求め、悪事をして幸いを求めても、得られるわけがない。(中略)人はこの道理をわきまえて、米がほしいと思えば米を蒔き、幸いが得たいと思えば善行をすればよい」(『二宮先生語録』斎藤高行著より)
これは現代経営における「戦略」と「実行」の一致の重要性を説いています。素晴らしい計画を掲げながら、日々の行動が伴わなければ、望む成果は得られません。結果とは、日々の地道な行動の積み重ねによってのみもたらされるという、ビジネスの基本原則です。
さらに尊徳は、成果が生まれるプロセスは、単一の要因ではないと指摘します。米作りを例に、自社の努力(農功)はもちろん重要ですが、それだけでは成功できないと説きます。市場環境や景気といった天の時(天恩)、そして顧客や社会といった事業の土壌(地徳)があって、初めて成果は実るのです。成功を自社だけの力と驕らず、全てのステークホルダーへの感謝を忘れてはならないという教えです。
尊徳の因果論の真骨頂は、その「時間軸」にあります。彼は、因果応報の結果はすぐには現れないからこそ、人々は道を誤ると警告しました。
「善因には善果があり、悪因には悪果を結ぶことは、だれでも知っていることだ。(中略)具合の悪いことに、今日蒔く種の結果は、目前に現れないで、十年、二十年から四十年、五十年の後に現れるものだから、人々は迷ってしまって、恐ろしさを感じない。(中略)世の中万般の事物は、原因がないものはなく、結果のないものもない。(中略)決して迷ってはならない」(『二宮先生語録』斎藤高行著より)
これは、短期的な業績評価に追われる現代企業が陥りがちな罠への痛烈な批判です。人材育成や研究開発といった「善い種」は、成果が出るまでに長い年月を要します。リーダーの役割とは、短期的な誘惑に惑わされず、長期的な視点で、未来のために正しい種を蒔き続ける信念と忍耐力を持つことなのです。
尊徳の教えは、目先の利益にとらわれず、誠実に正しい種を蒔き続けることこそが、持続的な成功への唯一の道であるという、不変の真理を示しています。
二宮尊徳(金次郎)について知りたい方、学びたい方は拙書「教養として知っておきたい二宮尊徳」(PHP新書)をAmazon(https://amzn.asia/d/dOAge1d)でご購読ください。お陰様で第10版のロングセラーとなり好評発売中です。
#松沢成文 #歴史 #二宮尊徳 #神奈川






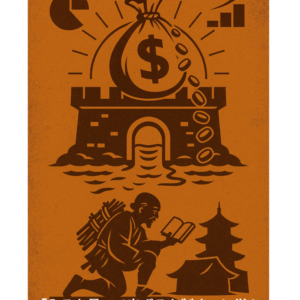

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
