『STOP受動喫煙新聞』第47号(’24年7月発行)掲載=脱法的営業が常態化する「喫煙目的店」④(最終回)=表示の不備、違反を取り締まらない、法令が曖昧…の諸問題
脱法的営業が常態化する「喫煙目的店」④(最終回)
表示の不備、違反を取り締まらない、法令が曖昧…の諸問題
公益社団法人 受動喫煙撲滅機構 理事
前神奈川県知事・参議院議員
「国際基準のタバコ対策を推進する議員連盟」幹事長 兼 事務局長
松沢 成文
=発行・「公益社団法人 受動喫煙撲滅機構」= https://www.tabaco-manner.jp
このテーマ最終回となる今回は、「喫煙目的店(施設)であることの表示行為」を取り上げるとともに、今後の対策について考えていきます。
まず喫煙目的店の表示については、健康増進法第35条第2項で次のように定められています。
喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。
一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
表示の規則は不十分
ご覧になったことがある方もいらっしゃると思ますが、この「掲示しなければならない」標識(以下「ステッカー」)の表示例として、厚生労働省は公式サイトで図のようなサンプルを掲載しています。しかし、このステッカーは、保健所等の行政機関から公的に交付されるものではなく、必要事項さえ記載されていれば自作も可能とされています。また、同法の施行規則では「記載された事項を容易に識別できるようにするものとする」とされているのみで、ステッカーの表示場所やサイズは、具体的に定められていません。
そうしたことから、目立たない場所やサイズでしかステッカーを表示せず、それ以上に「全席でタバコを吸えます!」と大きな看板などで掲示する飲食店が多く存在しています。
そこで、この表示についての改善策としては、まず喫煙目的店を保健所等の「許可制」とした上で、許可を受けた喫煙目的店のみが交付された専用のステッカーを、目につく出入口付近に掲示すること、と義務付けるよう、あらためるべきです。
「目的店」定義に反した違法営業が横行する理由
これまで4回にわたり、脱法的営業が常態化する「喫煙目的店」の問題を取り上げてきましたが、改めてこの問題の本質を以下に示します。
「喫煙目的店」営業をするための、法律上の主な条件は、
1、米やパンなどの主食を提供しないスナック・バー等であること
2、タバコの対面販売を行うこと
3、喫煙目的店であることの表示を行うこと
以上3点です。つまり、喫煙目的店の本来あるべき姿は、端的に言えば、
「本来、想定していた『シガーバー』のように、調理を伴わないスナック類等とアルコール類を提供するだけの店舗に制限する」
ということです。しかしそれらが守られず、主食を出し、タバコ販売を行なっていない「喫煙目的店」が横行、増加しているのです。なぜそうなったのか。それは、それら違反店はもともと、本来の「喫煙目的店」(いわば喫煙専用店)として営業する意図はなく、一般の「飲食目的」店で喫煙営業をしたいのですが、改正健康増進法では全面施行(’20年4月)以降に新規開業した一般店は禁煙にしなければならず(東京都と千葉市はさらに既存店でも人を雇っていれば禁煙)、しかし「喫煙目的店」(条件を満たした)なら営業可能としているため、〝抜け道〟方策として、単に「喫煙目的店」表示をして、違法の飲食営業をしている、ということなのです。
罰則があるのに適用せず、勧告もなし
また、改正健康増進法では、「喫煙目的店」として法律が定めた条件を満たしていない場合には、自治体は、供用停止の勧告を行い、これに従わない場合には、50万円の過料を科すことができます。しかし、制度が始まって4年が過ぎた現在もなお、どの違反店に対しても罰則の適用はなく、ほとんどの自治体で勧告すらろくにしていないようです。
このよう状況では、条件を満たさず法律に違反した飲食店等が、「そんな法律など、守る必要はない」と考えても不思議ではありません。
そもそも法があいまい
このように取り締まりすら行われていないことの原因は、既に述べたように(連載①)、担当する自治体の保健所の職員が’19年からの新型コロナ対応で忙殺されてきたというだけではなく、健康増進法の規定や定義があいまいなため、明確な基準に基づいて施設への指導がしにくいという問題があります(※)。
私はこの点についても、厚生労働省へ改善を働きかけるとともに、受動喫煙を防ぐ社会の実現に向け、全力で取り組んで参ります。
(’24年6月24日記)
※現行の法令でも、やる気があればでき、少なくとも勧告くらいはやれるはずですが、あいまいな条項が、自治体が動かないことの言い訳になっている、ともいえます。
図 厚労省が示している「喫煙目的店」掲示の〝サンプル〟

’24年6月6日、参議院外交防衛委員会で「JTのロシア事業」に関する質疑を行う筆者

☆『STOP受動喫煙新聞』紹介・購読案内はこちら

今号ほかバックナンバー一覧





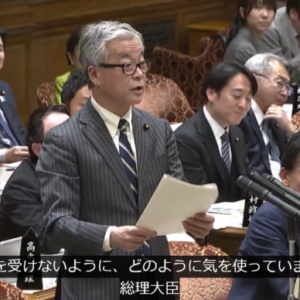

 松沢しげふみチャンネルを見る
松沢しげふみチャンネルを見る
